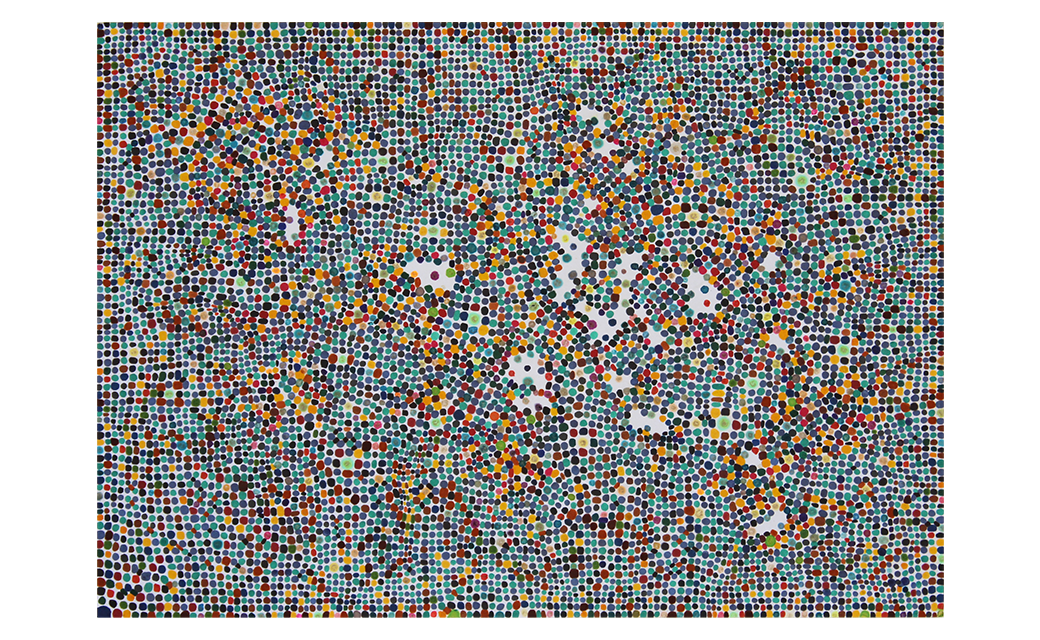伊勢 英子(画家・絵本作家)
2015年1月1日 更新
伊勢 英子
このコーナーでは、教科書教材の作者や筆者をゲストに迎え、お話を伺います。教材にまつわるお話や日頃から感じておられることなどを、先生方や子どもたちへのメッセージとして、語っていただきます。
ここ10年ぐらいで、絵だけではなく文章もご自身で書かれることが多くなっていますね。
絵描きとして、すてきな作家の先生たちと出会い、仕事をしてきました。例えば、松谷みよ子さんの『モモちゃんとアカネちゃんの本』シリーズ(講談社)の世界なんて、大好きです。そういう、「ああ、すばらしい文章だな」と思える作品を書かれる方に多く巡り会ってきて、たくさんの勉強をさせていただきました。
ただ、私は、その作家の専属なわけではないんですよね。あるとき、知らず知らずのうちに作家によって挿絵を描き分けている自分に気がついたんです。「松谷みよ子さん用の私」や「いぬいとみこさん用の私」のように。もちろん、他の人から見れば、どれも「伊勢英子の絵」のように見えるでしょう。でも、うまく説明はつきませんが、自分では描き分けているように感じられました。それで、「自分はこういうふうにしか描けない」というところで仕事がしたいと思うようになったんです。
「自分の」表現を強く求めるようになったということなのかもしれませんね。
同時に、作家が書く文章に折り合いをつけて挿絵を描くことの難しさも感じるようになっていました。例えば『海のいのち』でいえば、文章を読んだとき、私はどうしても「海のどんな表情でも好き」とは思えなかったし、そんなふうにさらっと言えるものではないと思いました。でも、やはり文章は作家のものですから、作家に「これでいきます」と言われればそれを受け入れて絵を描かないといけません。いちばん最初の読者である絵描きの私にとって、わからなさが残る文章——それに対して絵を描かなければならないことに違和感を覚えるようになったんです。しかたのないことなのかもしれませんけどね。
そのようなことがあって、文章も絵も自作するということを始めるようになったんです。

「旅する絵描き」(中学校「国語」教科書2年に掲載)と絵本『ルリユールおじさん』には、共通した世界が描かれていますね。同時進行で制作されたものだと聞いていますが、二つの作品はどのように生まれたのでしょう。
プライベートでパリを訪れたときのことです。街をぶらぶら歩き回っていてたまたま目にした小さな窓。これがきっかけとなり、『ルリユールおじさん』(講談社)の絵本ができました。窓のそばに「Relieur(ルリユール)」と書かれた看板も下がっていたのですが、そのときは気づかず、ただ、そこに並んだ背表紙から、「これは本に関係する窓だな」と思いました。ガラスの向こう側には、手作業で糸をかがっているおじいさんの姿も見えました。でも、そのときは、のぞいただけで帰ってきてしまいました。
しかし、一度ひかれてしまったものは、もう頭から消えないものですね。東京に戻ってきているのに、寝ても覚めても「あの窓の中に何かが。あの窓の中に——」ということばかりが気になる。それで、その1か月後、もう一度パリに行ったんです。
とにかく「行けば何かがある」という直感がありました。今まで私は、「そこに行けばこんな未来が約束されている」と思ってどこかに行ったことはないんです。いつも本能のままに動く。ですから、「あの窓の中に何かがある。あのおじいさんに会えば何かが始まる」という、その一心で向かいました。
何が始まると思ってらっしゃったのでしょう。
なにしろ直感ですから、理屈で語れないのですが——。手作業で糸をかがっていましたから、「手仕事」の職人だということは、初めて見たときにわかっていたんです。80歳ぐらいの、がんこそうなおじいさんが淡々と作業を続けている。その動きやたたずまいの確かさは、「おじいさん」などと呼ぶのは失礼に思えてくるほどでした。その年になるまで自分の手でする作業を続けているんですよ。長い歴史があるはずです。とにかく会ってお話をうかがったら、これまでいったいどんなことをされてきたのかがわかるという思いがありましたね。「物語は後からついてくる」と。
ずっと先があらかじめ見えているわけではないんです。本当に、階段を一段一段上るような感じです。下にいるとき、上の段は霧がかかって見えないのですが、一段上がれば霧が晴れて見えるようになる。そうしてまた一段上る。その繰り返しですね。

まるで何かに導かれているようですね。
結果論ですが、今、思い返すと、この『ルリユールおじさん』に費やした2年間には、本当に多くの偶然が散りばめられていたような気がします。パリで滞在していたアパートが、実は、ルリユールおじさんのお父さんの工房があった建物の隣の隣だったとか、「ええっ」と思うようなたくさんの偶然がありましたね。
『ルリユールおじさん』と『旅する絵描き』に出てくる樹齢400年のアカシアの木も、たまたま私のアパートの窓から見える風景の一部だったんです。探そうと思って探したものじゃないんですよ。毎日毎日、窓からこのアカシアを眺めていると、その下を通り過ぎていく人々の足が見えて、「ああ、足の数だけ物語があるんだなあ」と思えてきたものです。『ルリユールおじさん』の、女の子が本を直してもらうというストーリーの着想は、このアカシアの下を走っていく女の子の足から得たんですよ。表紙にもその風景が描かれているでしょう。
それから、キャンバスの話。私は、ゴッホが好んでよく使っていた、サイズ比率1:2のキャンバスで描くのがいちばん描きやすいのですが、この比率のキャンバスは、日本ではどこにでもあるものではないんです。でも、フランスにはいろいろなキャンバスがあります。あるとき画材店で、70×140センチという、1:2の比率の大きなキャンバスを見つけたんです。「ああ、これはすごいな。これにアカシアを描いたらすばらしいだろうな」という思いがむくむくとわいてきましたね。すぐに買って、アカシアの下を走っている女の子の絵を描きました。のちに『ルリユールおじさん』の表紙の元となったタブロー(絵画)です。
そうしたら、「もうこれで本ができたようなものだ。もうわかった。ここから全てが始まる」という気持ちになったんですね。だから、この物語の骨格は、この1枚のタブローから生まれたんです。もちろん、東京に戻ってから、細部を調べ、物語の調整をする作業は必要でしたけれどね。

樹齢400年のアカシアが、物語が生まれる鍵となっていたのですね。
『ルリユールおじさん』は、本に関わる「手」の職人が、本の大好きな女の子のために、本を直してあげる話で、そう考えると、「人の手と手の話」だといえますよね。だから、女の子も、手で本を抱きしめている。それから、もう一つには、「職人の話」でもある。
でも、この物語を陰で支えているのは、実は400歳のアカシアだと思っています。もしこのアカシアが出てこなかったら、本を直すという400年の伝統文化も、その間の無数にある人々の物語も見えてこない。ルリユールおじさんは、女の子の本をたったひと晩で直してしまいますが、それは本の文化、本を直す文化という背景があってこそのことです。だから、おじさんや女の子の年齢をも超えて、定点観測のように、一つの場所、一つの視点でずっと見ている証人みたいなアカシアはとても重要なんです。それがなかったら物語はもっとずっと浅いものになっていたかもしれません。
そういう意味で、だれも気づかないかもしれませんが、この物語の陰の主人公は400歳のアカシアだと、私は本当に思っているんですよ。
『旅する絵描き』の文章も、『ルリユールおじさん』のためのパリ滞在と同じ時期に書かれたのですよね。
そうなんです。『旅する絵描き』は、理論社という出版社のホームページに連載したエッセイを改稿して、スケッチを加えて構成し直した本なんです。私が何度もパリへ取材に行くものですから、理論社の方が、「ホームページに載せるエッセイを書いてください」とおっしゃったのが始まりです。ですから、『ルリユールおじさん』と世界観は同じです。
ただ、エッセイを書くにあたって、「伊勢英子」として書くことで、いかにも「私の取材日記を読んでください」というふうになるのがいやだったので、「ぼく」としたんです。『ルリユールおじさん』よりも前に出した絵本『絵描き』(平凡社)(※)に出てくる、旅する男の子のつもりでね。
- ※絵本『絵描き』 2004年に理論社より刊行後、2012年に平凡社より復刊される。
なお、『ルリユールおじさん』は、2006年に理論社より刊行後、2011年に講談社より復刊された。
絵本『絵描き』は、ゴッホを思わせる絵描きの少年、「ぼく」の生き方が描かれた作品ですね。
実は、ルリユールおじさんのところを初めて訪ねたときに持って行ったのがこの『絵描き』だったんです。「私はこういう絵を描いている絵描きです」という自己紹介の意味を込めてね。この絵本に出てくる「ぼく」の部屋は、ゴッホの部屋なんです。おじさんはフランス人だし、それがわかったのか、絵本を見て、「すばらしいデッサン力だ」「おまえは、見えないものを見ている。ゴッホと同じだ」と褒めてくれました。ひどく謎めいた言葉ですよね。もしかしたらジョークかもしれないとも、何か含みがあるのかもしれないとも思いましたね。
職人、つまり「アルチザン」というのは、「アーティスト」ではありません。自分のすべきことに徹し、それに正直であって、世間や流行がどうであろうと、すべきことを守り続けるという世界に生きている。絵描きの私とは見方が全く違います。それに、おじさんは、パリ以外の場所に住んだこともなければ、旅もしない。そこも私とは正反対。

でも、その「見えないものを見ている」という言葉を聞いて、私が一途に生きてきたことをわかってくれたんだなと思ったんです。一途にやってきた人には、一途に生きてきた人のことが理解できるんですね。私にとってはたいへんな褒め言葉でした。
「認めてくれた」ということなのでしょうね。
ええ。初対面にもかかわらず、「私のことを取材していいよ」と言ってくれました。私は、製本の工程を取材したかったので、この絵本『絵描き』を解体して金箔の装丁に修復し直すまでの作業をしてもらうようお願いしたんです。表紙を取って、皮をなめして——最後には金箔で「Hideko Ise」と書いてもらうというプロセスを、ずっとスケッチしていきました。
つまり、絵本『絵描き』が『ルリユールおじさん』へのパスポートになったわけですね。エッセイの語り手を『絵描き』の「ぼく」に設定したことには、そういう理由もあったかもしれません。
「旅する絵描き」の教科書掲載の依頼を受けたときの思いをお聞かせいただけますか。
たいへんうれしかったです。絵だけであれば「海の命」が、絵と文章の両方では「1000の風、1000のチェロ」が小学校の教科書に載っていますが、文章に注目されて載ったことはなかったので、「私の文章が国語の教科書に載るなんて、嘘みたい!」とびっくりしました。
『旅する絵描き』は、もともと、理論社のホームページで公開後、1か月したら消えていく運命だったエッセイを、「いい文章だから」と平凡社が本にしてくれたものです。それが今度は、光村図書さんが「いい文章だから」と、教科書に載せてくれたわけですよね。二重三重に連なって形になったというのが喜びでした。

それから、この文章の「ぼく」が生まれた絵本『絵描き』を世に出したときの思いも関係しているかもしれません。当時、中学生だった娘が、髪の毛を青く染めたり爪を青くしたりという、反抗期の真っただ中にありました。「ジベタリアン」なんていう言葉もありましたけれど、まさにそんな感じの生活を送っていました。反抗期って、悩みの渦の中から抜け出せない時期なんでしょうね。だから、もがく。みんないい子なのに——。
絵本『絵描き』は、そういう若い人たちが立ち上がるようなことをしなければという思いで作ったものだったんです。「なんでもいいから立ち上がって旅しなさいよ」「自分の力で歩いていきなさいよ」っていうつもりでね。そして、そこに出てきた「ぼく」が「ぼくの歩き方でいいんだ」ということを見つけるのが、この『旅する絵描き』。そういう作品を光村図書さんが採用してくれたっていうことが、本当にうれしかったんです。「こうやって旅をしてて発見することで自分の人生が形を成していくんだよ」っていうことを認めてもらえたような気がしました。教科書には初めのほうの部分しか載っていませんが、きっと、そういう私の思いに気がつく子はいるんじゃないかなと思っています。
Photo: Shunsuke Suzuki
伊勢 英子 [いせ・ひでこ]
画家・絵本作家。1949年、北海道札幌市に生まれる。東京藝術大学デザイン科卒業。大学を卒業して、1年間フランスに留学。帰国後、児童書の挿絵や絵本の制作を手がけるようになる。絵本『むぎわらぼうし』による絵本にっぽん賞受賞をはじめ、野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞美術賞、講談社出版文化賞絵本賞など受賞作多数。代表作「ルリユールおじさん」「1000の風 1000のチェロ」「にいさん」ほか、フランスなど海外で翻訳・出版されている絵本も多い。絵本制作と並行して絵本原画展、アクリル画の個展を各地で開催。光村図書小学校「国語」教科書6年には「海の命」(挿絵)、中学校「国語」教科書2年には「旅する絵描き」が掲載されている。