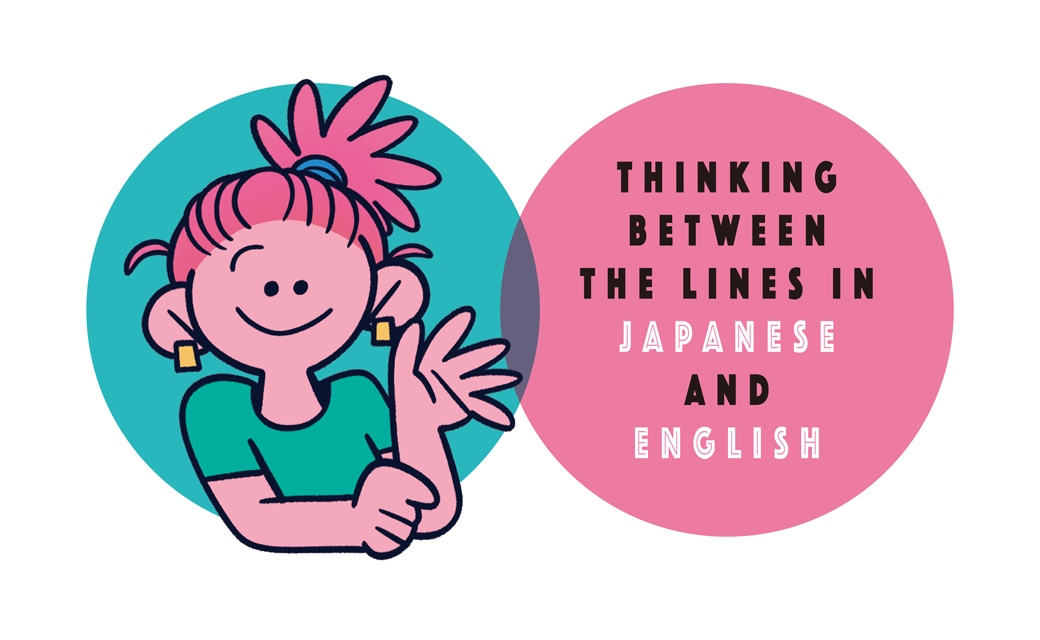子どもの心を耕す外国語活動
2016年7月1日 更新
加賀田 哲也 大阪教育大学教授
「かかわり合い、伝え合い、つながり合う」ことを目ざした、小学校英語の実践をご紹介します。
加賀田哲也(かがた・てつや)
1965年福岡県生まれ。大阪教育大学教育学部教授。米国シアトルの州立ワシントン大学(理論言語学)および大学院(教育心理学)を修了後、大阪大学大学院人間科学研究科博士課程後期修了。博士(人間科学)。大学で教員養成に携わる他、小学校、中学校、高等学校などで英語授業改善のための指導や教員研修に当たっている。光村図書中学校英語教科書『COLUMBUS 21』編集委員を務める。
第3回 I Am Special! (1)
今回は「I Am Special!」というアクティビティを紹介します。日本の児童・生徒の特徴として、自尊感情や自己信頼感の低さが指摘されていますが、このアクティビティは、友達のよさを褒めたり、友達から指摘された自分のよさを受け入れることで自分や他者に対する理解を深め、自分や他者を大切にする気持ちを育んでいくことをねらいとしています。
このアクティビティは、道徳と外国語活動の合科授業となります。
まずは、道徳の時間にグループになり、メンバーのいいところを考えて、以下のように指摘していきます。
- ○○さんの「おもしろい」ところが好きです。なぜなら、「いつもクラスのみんなを笑わせてくれるから」です。
そして、外国語活動では、このときに出された性格等を表す代表的な単語を次のように英語に直し、下記のような会話をします。
active(活発な) kind(親切な) funny(おもしろい) friendly(フレンドリーな) helpful(手伝ってくれる)
polite(礼儀正しい) charming(チャーミングな) など
A: Hello, ○○. I like you. You are kind.
B: Yes, I am kind. Thank you.
A: You’re welcome. + 理由を述べる(日本語でも可)
教師はあらかじめ、右のような、性格が表された小さいサイズの絵カードを用意し、子ども達は会話をしながら該当するカードを相手に渡していきます。
ここで大切な点は、上のB さんのように、相手からもらった言葉 “You are kind.” を “I am kind.” と自分に言い換えることで、自分自身を受け入れ、よいところに気づかせることです。そして、一言一言に気持ちを込めて表現するよう促します。

理由は日本語で言ってもいいことにします。その場合は、「今は言えなくても、中学校で一生懸命勉強すれば必ず言えるようになるよ」と一言添えれば、中学校での英語学習への動機づけを高めることにもつながるでしょう。
このアクティビティの端緒となる“I like you.” という言葉は、日本語では恥ずかしくてなかなか言えないかもしれませんが、「外国語活動」の場面であれば、心のハードルも下がり、気持ちを込めて言ってくれることでしょう。
実際の授業で子ども達から出された相手のいいところとその理由について一部紹介します。
- A-san is helpful.
理由:自分が困っているときに、いつも「大丈夫」と声をかけてくれて助けてくれるから。
- B-san is funny.
理由:落ち込んでいるときに、おもしろいことを言って楽しませてくれるから。
- C-san is active.
理由:体育のときに、いつも活躍しているから。
この授業の振り返りでは、子ども達から次のような言葉が聞かれました。
- 初めは素敵な言葉を使うのにとまどったけど、何度もやっていると、友達のいいところがたくさん浮かんできてよかったです。
- 自分のよいところをたくさん言ってもらって、うれしかったです。
- 自分が思っているカードと違っているカードをもらって、びっくりしました。
- いいところをたくさん伝えたり、伝えてもらったりするのはうれしかったです。これからも使っていきたいと思います。
また、実はこのクラスには、特別な支援を要する子どもが数名いました。普段のインタビュー活動ではなかなか相手を見つけようとしなかったり、見つけられなかったりする子ども達が、この活動では積極的に相手を探し、言葉を交わしていた姿がとても印象的だったと、担任の先生が話されていました。
最後に……。
ある子どものこの日の日記には、「今日の英語の時間で、クラスのみんながもっと仲良くなったと思う」と書かれていたそうです。この言葉は、このアクティビティを通して、クラスの子ども達がまさに「つながり」や「一体感」を感じ取ったことを表しています。また、学年末には「6年生になってもこのクラスのままでいたい」という声が聞かれたそうです。
次回は、「I Am Special!」の第2回として、五行詩を作って自分をアピールする活動をご紹介します。
Illustration: Atsushi Hara