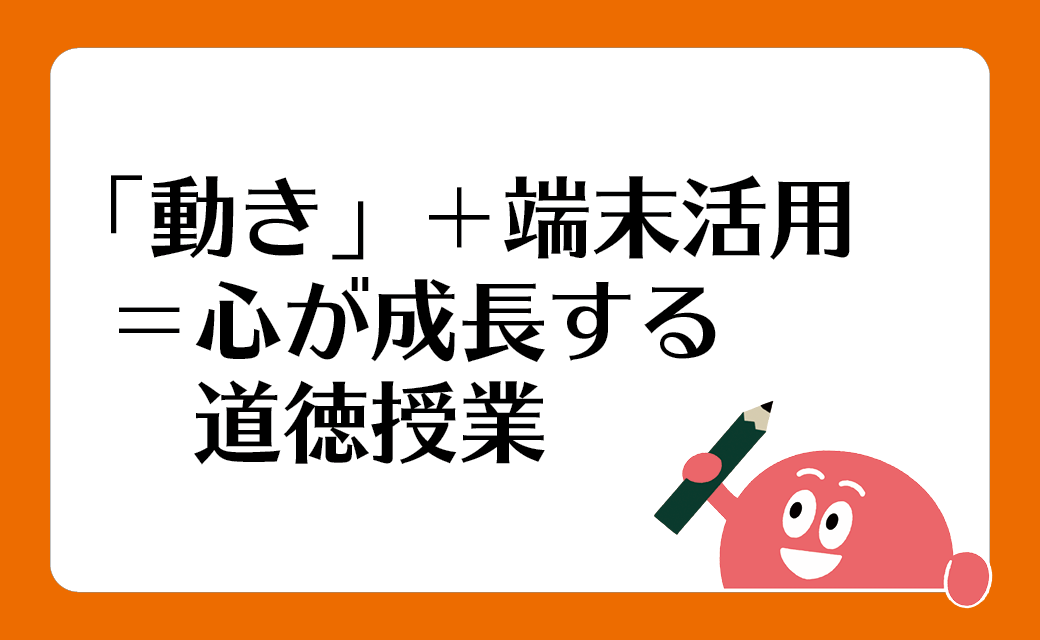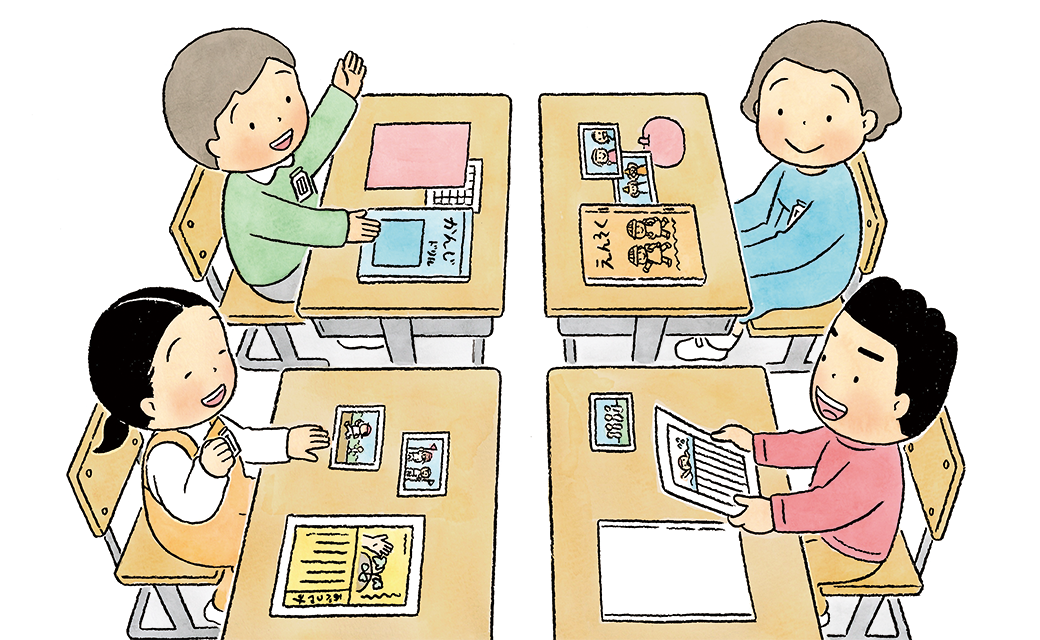「自画像」のひみつ
2015年8月7日 更新
藤原 えりみ 美術ジャーナリスト
「自画像」にはこんなひみつがあった! 自画像をめぐるさまざまエピソードとその見方をご紹介。
藤原えりみ(ふじはら・えりみ)
1956年山梨県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了(専攻/美学)。女子美術大学・國學院大學非常勤講師。著書に『西洋絵画のひみつ』(朝日出版社)。雑誌『和楽』(小学館)、『婦人公論』(中央公論新社)で、美術に関するコラムを連載中。光村図書高等学校『美術』教科書の著作者でもある。
第5回 フリーダのまなざし ―自己演出としての自画像―
ゴッホとアルルで共同生活を送ったゴーギャンもまた、数々の自画像を残している。共同生活の破綻の原因となった二人の芸術観・絵画観の相違が、彼らの自画像にも表れているのがおもしろい。ゴッホの場合、自画像制作は自己確認のまなざしを秘めつつも色や形態の実験でもあった(第4回参照)。常にモデルや具体的な事物のモチーフを必要とするゴッホに対して、「想像で描くべきだ」と意見したというゴーギャン。彼の自画像には、「かくあるべき私」ないしは「かくありたい私」という、ある種の理想化への傾向をうかがうことができる。
その一例として、自らをキリストになぞらえた作例(※1)を挙げてみよう。キリストといえば、デューラーの作例が思い浮かぶが(第2回参照)、光輪をいただいたゴーギャンの姿には、明らかに「芸術に殉ずる私」という自己イメージが重ね合わされている。ゴーギャンにはキリストの磔刑図を描いた自作品を背景とする自画像(※2)もあるため、芸術家の理想像としてだけでなく、彼自身の信仰告白である可能性もあるのだが、それにしても大胆な試みのように思われる。
※1 「光輪のある自画像」ポール・ゴーギャン(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)
※2 「黄色いキリストのある自画像」ポール・ゴーギャン(オルセー美術館)
どうもこのような自己演出(「かくありたい私」志向)は、男性画家の自画像に散見するような気がするのだが、思い過ごしだろうか。たとえば、ギュスターヴ・クールベ。いかにも「ダンディ」な伊達男姿の「犬を連れた自画像」(※3)や、芸術的狂気をはらんだ「絶望(自画像)」(※4)などを見ると、「この人どれだけナルシスト !?」と、思わずつぶやきたくもなる。まあ、女性画家の場合でも、マリー・アントワネットの肖像画で知られるエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランなど、才気溢れる若々しい才媛としての自画像を残しているケースもあるのだから、自己演出は男性のみの特権(?)とは言えないのだろうけれども。
※3 「犬を連れた自画像」ギュスターヴ・クールベ(パリ市立プティ・パレ美術館)
※4 「絶望(自画像)」ギュスターヴ・クールベ(オルセー美術館)
そして、女性画家と自画像といえば、この人を忘れるわけにはいかないだろう。20世紀メキシコを代表する画家フリーダ・カーロ。彼女は、病気と交通事故による身体的苦痛や精神的な苦難を抱えつつ、自立した女性としての生き方を模索した。虚弱な身体を補完するかのように華やかなメキシコの民族衣装に身を包み、自らの身体を通して女性の「生と死」を描き出そうとした。その気迫溢れる画面に圧倒される。
※5 「いばらの首飾りとハチドリの自画像」フリーダ・カーロ(ハリー・ランサム・センター)
彼女の夫は、メキシコの壁画運動を代表する画家ディエゴ・リベラだが、彼もフリーダの才能を高く評価していたという。また、シュルレアリスト・グループの総帥アンドレ・ブルトンも彼女の作品を絶賛した。だが彼女自身はシュルレアリスムとは距離を置く。「私が描くのは夢ではなくて、私の現実なのだから」と。リベラの女性関係に苦しみ、自らもイサム・ノグチやレオン・トロツキーと浮き名を流す恋多き女でありながら、実はひたすらリベラを愛し続けたといういたいけな側面ももつ。
自らの身体的欠損をえぐり出すような自画像もあれば、大地と直結することで安らぎを得ようとするような自画像もある。彼女にとっては絵の中の世界こそ「現実」であり、その「現実」なくしては生きていくことができなかったのだろう。夢と見えて実は夢ではなく、演出と見えて実は演出ではない。フリーダが見通していたのは命の危うさと生きていることの歓び。そのまなざしは限りなく優しく温かく、今も私たちを包み込む。
次回は、森村泰昌の作品を例に、「他者としての自己」をご紹介します。