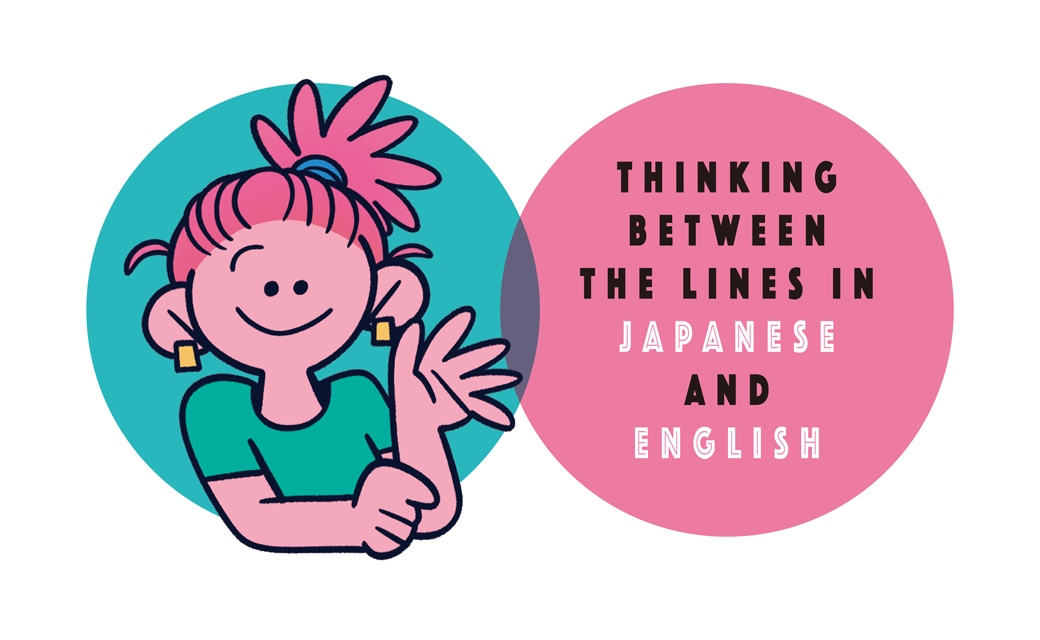小学校英語 指導と評価
2021年8月25日 更新
黒木 健 横浜市立斎藤分小学校長
小学校英語の評価について、先生方の悩みに寄り添いながら解説します。
黒木 健(くろき・けん)
横浜市立斎藤分小学校長。
上智大学文学部教育学科卒業。これまでに横浜市立洋光台第四小学校長、横浜市立矢部小学校長、横浜市立小山台小学校長、神奈川県小学校外国語活動研究会部会長、横浜市小学校外国語活動・外国語研究会副会長などを歴任。
第3回 「振り返りシート」の活用による自己評価について
今回は、「振り返りシート」から得られた児童の具体の反応に触れ、それを分析することで、①教師の指導改善につながるもの、②児童の学習改善につながるものの二つの観点から考察を加えていきたい。
外国語科における振り返りシート
外国語科における「振り返りシート」は、児童への問いかけとして、「楽しく活動できたか」、「英語を聞けたか」、「英語を話せたか」、そして最後に自由記述といったように、その単元で育成する資質・能力がはっきりしない、またパターン化されたものが多かったようにも思える。しかし、昨年度より教科化がなされた5・6年生については、「主体的に学習に取り組む態度」を見ていくための手段の一つとして、「振り返りシート」が大切な役割をもってくる。そしてそれを使い、児童の反応をしっかりと分析し、それらをどう活用していくかについて、教師側に明確な見通しをもつことが求められる。

児童が振り返りをする際の教師側の手立て
では、どのような視点をもった上で、「振り返り」を行っていくべきなのかについて、次に考えてみたい。
まず押さえておきたいこととして、「振り返り」の時間で、教師がその授業における児童の頑張りを認めるコメントをした上で、本時のめあてを再確認し、「振り返りシート」に記入させるようにしていくことが望ましいことは言うまでもない。ただそこで、どのような「振り返りシート」を作成するかに焦点を当てるだけでなく、実際に児童から得られた「振り返り」の中から、どのような「振り返り」をさせることが児童の実態により合致していて、且つ育成したい資質・能力を伸ばしていくことにつながるのか、あらかじめ教師がそのイメージをもつことは、欠かすことのできない点である。
教師が本時の目標から、ぶれないような授業展開を行っているか、単元目標つまり、ユニットのゴールにおける本時の役割を意識した授業になっているか、また振り返りの際に本時のめあてを確認して、児童が「できた」かどうかを自己評価しているかなど、児童が自己評価するための手立てがしっかりと講じられているかが肝要となる。
◆児童の振り返りシート例

子どもたちの具体の反応から考える
これまでの指導の中での「振り返りシート」における児童の「振り返り」をいくつか取り上げ、その意味について考えてみたい。
「主体的に学習に取り組む態度」を評価するための「振り返りシート」コメント欄の分析
児童A
| 第1時 世界の国の言い方を上手に言えた。 | 第6時 「行きたい。」って感じを出せた。 |
第1時では、国名を表す語句に慣れたことについての記述。
第6時では、行きたい国紹介の準備をする際に、自分の気持ちを込めて言えたことについての記述。
児童B
| 第3時 英語を間違えずに言うのを頑張った。 | 第7時 少し止まってしまうところをもあったけど、ちゃんと言えた。 |
第3時では、「話す技能」について正確さを心がけたことについての記述。
第7時では、暗記ではなく、本当に言いたい自分の考えは何かを整理しながら話している記述。
児童C
| 第1時 CDの内容を聞き取れました。 | 第7時 行きたい国の「よさ」を聞けました。 |
第1時では、音声DVDを聞き取ったことについての記述。
第7時では、行きたい国の紹介を友達と聞き合ったことについての記述。
児童D
| 第6時 しゃべった。 | 第7時 しゃべれなかったけど、言えた。 |
第6時では、紹介したい国について発表したことについての記述。
第7時では、自然な話しぶりをしている感じではなかったものの、発表はできたという記述。
児童E
| 第4時 もう少しすらすら話せるようにする。 | 第7時 deliciousをbeautifulと言ってしまったが、すらすらと言えた。 |
第4時では、行きたい国とその理由をつかえながらもやり取りできたことについての記述。
第7時では、語の言い間違いをしたものの、発表そのものはできたことについての記述。
児童F
| 第2時 先生とか動画の人が言っている意味を全部わかりたいです。 | 第7時 発表では、相手の目を、前より見て話せた。 |
第2時では、教師のスモールトークや音声DVDを聞いたことについての記述。
第7時では、目線を相手に向けることを意識した発表ができたことについての記述。
児童G
| 第2時 前よりちょっと忘れているところがあって、聞き方を工夫した。 | 第7時 練習ではできたけど、発表では緊張してごちゃごちゃになっちゃった。 |
第2時では、第1時で聞いた音声DVDの聞き取りと比べて、聞くことができたことについての記述。
第7時では、相手に伝える意識はもったものの、思うようには発表できなかったことについての記述。
児童H
| 第4時 小さな声だったけど、言葉を言えた。 | 第6時 間違えてしまったけど、中国はいい国だと伝えることができた。 |
第4時では、行きたい国とその理由を話すことができたという技能についての記述。
第6時では、語句の言い間違いはあったが、行きたい国の魅力を伝えられたことについての記述。
児童I
| 第3時 先生の話を聞き、先生からの質問に答えることができました。 | 第6時 自分が間違えていても、立て直せたのでよかったと思いました。 |
第3時では、教師の問いを理解し、それに答えることができたことについての記述。
第6時では、自分がどう間違えたかに気づくことができ、自己調整して発表できたことについての記述。
このように、個々の児童の振り返りの言葉を的確に翻訳し、その意味と変容を把握することが大切である。
さらに、「主体的に学習に取り組む態度」を見取るための「振り返りシート」であっても、事項に述べるような活用も考えられる。
教師の指導改善につながるもの
上記児童の「振り返り」から言えることは、「知識・技能」、「思考・判断・表現」の評価に重きを置いた授業の時であっても、本時のめあてに沿った振り返りの指導を行うと、「主体的に学習に取り組む態度」を見取るための「振り返りシート」も本時目標を達成できたかに則した記述になる可能性が高まるということである。
「知識・技能」を見取る授業においては、本時の振り返りの直前に、本時の言語活動を再び教師が児童に投げかけることで、「どういう姿になっていれば、『できた』ことになるのか。」を児童に確認させることができる。例えば「行きたい国とその理由を尋ねたり答えたりする言い方を知る。」ことが本時のめあてであった場合は、振り返りの前に改めて、
T: Where do you want to go?
S: I want to go to Peru.
T: Why?
S: I want to visit Machu Picchu.
といったような「やり取り」を数名の児童に対して全体の前で行うことで、どの児童も「今日は何ができるようになればよかったのか」を改めて認識しやすくなる。
また「思考・判断・表現」を見取る授業においては、本時の活動を振り返り、「表情豊かに、目線を相手に向ける、はっきりした声を出す、相手の話に反応を示していたのはどこの班の発表だったか。」など、班ごとの国の紹介の仕方を振り返る視点を明確にした上で、ペアまたはグループやクラスで話し合ってから記述を行った方が、児童も本時のめあてに則した内容を書きやすくなるものと言える。
児童の学習改善につながるもの
最後に上記児童の「振り返り」から、「振り返りシート」を児童の学習改善にどうつなげていくかについて考えてみたい。
まず「振り返りシート」の冒頭に、単元名だけでなく、ユニットのゴールを明示することで、児童が「この単元の終わりには、何ができるようになればいいのか」という学習の見通しを立て、主体的に学習活動に取り組めるようにしたい。そして授業の始まりの際に、前回の授業の中からよかった振り返りを紹介し、「こんな工夫をしたら、こういうふうにできるようになった。」など、他の児童の振り返りから学ぶ時間を共有することも、今後の児童の学習改善へのきっかけを与えるものとして、大切にしたい点である。もし記述式の振り返りがあれば、その顕著な部分に赤線を入れるなどして、児童の努力を認めることで、次の学習への動機付けを高めることにもつなげたい。また各単元の終わりでは、教師がコメントを書き入れることで、この単元における言語活動を通して「何ができるようになったのか」ということを、児童自身がより明確に自認できるようにできれば、なおよいと言えるだろう。
【参考資料】
『小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック』(文部科学省 2017年)
『小学校学習指導要領 外国語活動・外国語編』(文部科学省2018年)
『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』(国立教育政策研究所 2020年)
『小学校外国語科(英語)指導書』(光村図書出版 2020年)
Illustration: 福々 ちえ
- このシリーズの目次へ
- 前の記事
-
次の記事