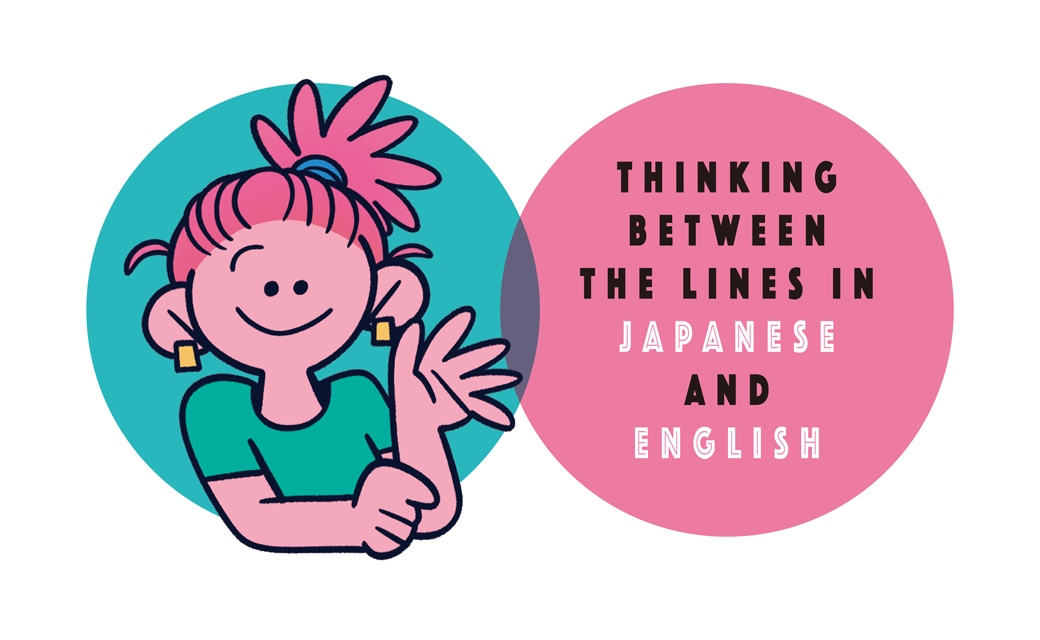
日本語と英語の行間で考える
2025年10月20日 更新
キニマンス塚本ニキ 通訳・翻訳家・ラジオパーソナリティ
幼少期より日本語と英語を使い分けながら、それぞれの表現やコミュニケーションについて考えてきたニキさんの視点で、これらの魅力や ままならなさをポップにライトにつづります。
第1回 「AIがあれば通訳はいらない」って本当ですか?
まさか自分が生きているうちにAIに仕事を脅かされる時代がくるなんて、ほんの数年前までは想像もしていなかった。フリーの通訳・翻訳業を15年ほどやってきた自分の世代なら逃げ切れるだろうと根拠もなくたかをくくっていたら、スマホの中の人工知能がいくつもの言語をほんの数秒で、しかもほぼ完璧な状態で変換できてしまうという衝撃の現実に直面している。自分が長年積み重ねてきた経験もスキルも、流行りの無料アプリごときに負けてしまうのかと思うと、なんともやるせない焦燥感にかられる。
とはいえ、ジタバタあがいても時代の変化は止められない。遠出をするなら駕籠(かご)担ぎに、恋文を送るなら代筆屋に、映画を観るときは弁士に、電話は交換手に、データ処理はキーパンチャーに。そうやって昔から頼られてきたいくつもの専門職が技術の進歩とともに自然淘汰され、職を失った人々は生きるために別の道を探さざるをえなかっただろう。わざわざ人間に翻訳や通訳をやらせるなんて時代遅れだ、と言われるようになるのも時間の問題かもしれない。
もちろん、こちらも一応のプロとして簡単に引き下がる気はないし、今後どれほど技術が発達してもAIがすべての異言語コミュニケーションを完全に代弁できるようになるとは思えない。これは技術がどうこうというより、人としての意地だ。本音を言えば、人間どうしの関わりを支える役割を、同じ人間でなくAIに頼る人が多数派になった世界を想像したくないのだ。
これまでいちばん苦労した通訳現場の一つに、ある有名なアメリカのロックスターと高名な日本人彫り師が同席した会食がある。酒が進むにつれ二人とも饒舌になり、昔の自慢話や大人のジョークから歴史や文化論などのインテリ話へと、楽しい会話が延々と続くなか、私は場の空気を壊さないように、笑顔のままトイレを我慢して必死に通訳しながらサラダやパスタを取り分けていた。3時間以上に及んだ怒涛のディナーが終わる頃には心身ともにヘトヘトだったが、「自分にしかできない大仕事を成し遂げた」という達成感とアドレナリンがみなぎっていたのを覚えている。知的好奇心と表現力あふれる多才な人たちの会食は、ただ言葉を変換するだけじゃなく空気を読みながら同じ好奇心とテンションを保てる人間が間にいたから成り立ったんだと自負している。そして言語も文化も世代も異なる、良くも悪くも人間臭くてクセの強い二人の「伝えたい、伝えてほしい」という気持ちが一致したからこそ、あの独特のグルーヴ感が生まれたんだろう。
人間どうしのコミュニケーションに完璧なんてものはありえない。思いつきで喋ったり、何を言いたいのかわからなくなったり、ちっとも噛み合わなかったりしながら、それでも何かを日々伝え合おうとしている。そんな気まぐれで不完全な人間のチグハグなコミュニケーションを補佐しようとする行為が人間を人間たらしめるんだと思う。たとえいつか世界中の人間の交流がAIを通して行われるようになったとしても、私は人として伝えようとする試みをやめずにいたい。
タイトルイラスト: 水沢石鹸
キニマンス塚本ニキ
通訳・翻訳家・ラジオパーソナリティ
1985年東京都生まれ。9歳から23歳までニュージーランドで暮らし、オークランド大学で社会学・ジェンダー学・映像学などを学ぶ。日本に帰国後、フリーの通訳・翻訳者として国内外の社会課題の啓発や対話の現場に携わる。TBSラジオ「荻上チキ・Session」やYouTubeチャンネル「ポリタスTV」などのレギュラー出演、雑誌コラムを通して発信中。著書に『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(Gakken)がある。
- このシリーズの目次へ
-
前の記事
-
次の記事














