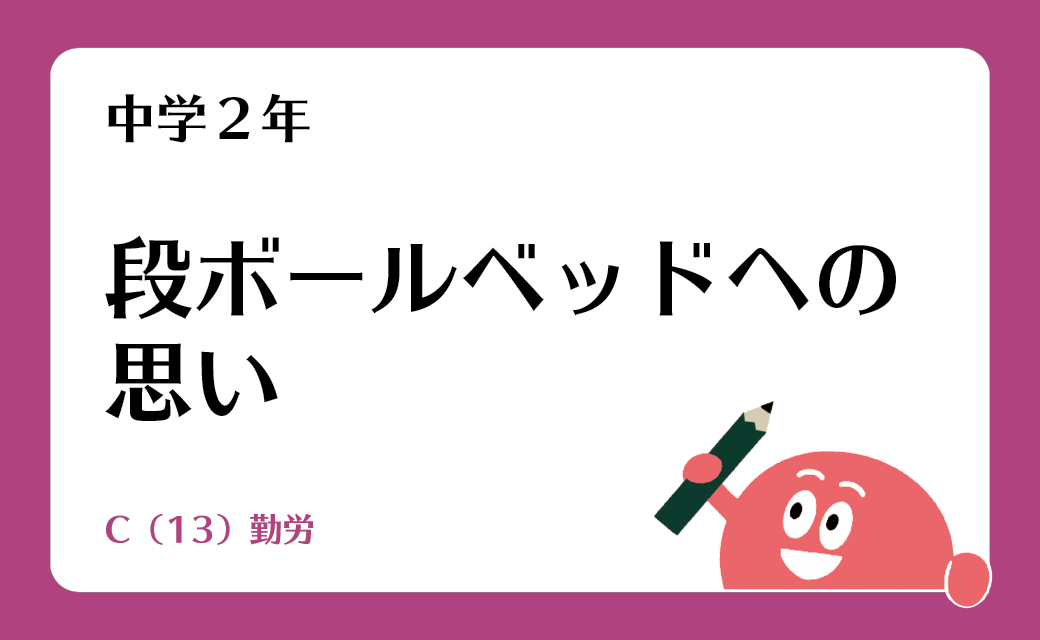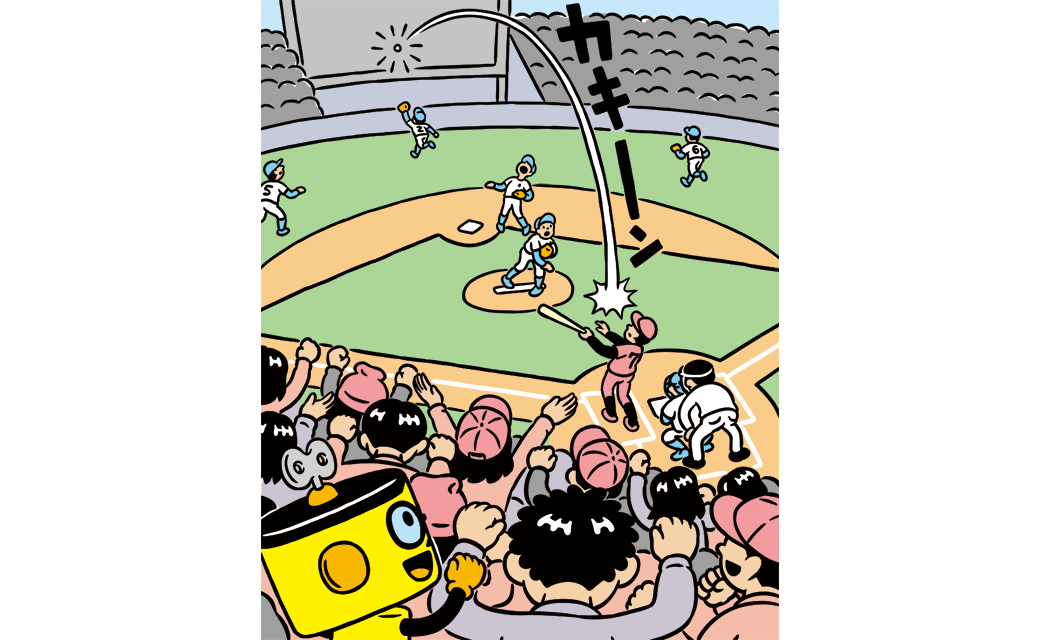「こんな授業ができます!」 令和6年度版小学校国語
2025年7月11日 更新
東泰右 香川大学教育学部附属坂出小学校教諭
2年上巻「みの回りのものを読もう」の授業づくりのアイデアを紹介します。
情報を伝えるための工夫に注目して読もう
単元観
身の回りの表示などの特徴を考える活動を通して、大事な情報を読み取る力を培う単元である。「もし、『あぶない』の言葉がなかったら。」などと、言葉の意味・働き・使い方に着目しながら考えるという国語科において重要な力を培うことにも適している。身の回りのものを題材として取り上げ、ICT端末を活用することで児童の意欲を高めたい。
- 「もし、~だったら。」の話型を用いることで、工夫がある場合とない場合を比較しながら、その効果について考えられるようにする。
- 実際に校内にある表示や看板を探す活動を取り入れ、児童の意欲を高める。
- ICT端末を用いることで、見つけた表示の撮影とその共有を容易にする。
単元の目標
身の回りの表示から大事な言葉を選び、伝えたいことやそれを伝えるための工夫を読み取ることができる。
評価規準
◎「読むこと」において、文章の中の重要な語や文を考えて選び出している。[思C(1)ウ]
○言葉には、事物の内容を表す働きがあることに気づいている。[知(1)ア]
〇「読むこと」において、文章の内容と自分の体験とを結び付けて、感想をもっている。[思C(1)オ]
○積極的に身の回りのものから重要な情報を読み取り、学習課題に沿って、考えを交流しようとしている。[主体的に学習に取り組む態度]
単元の授業過程(全2時間)
| 時 | 学習活動 |
|---|---|
|
1 |
①教科書P118のアの写真を見て、この看板が伝えていることについて話し合う。 |
|
2 |
①前時の学習を振り返り、本時のめあてを設定する。 |