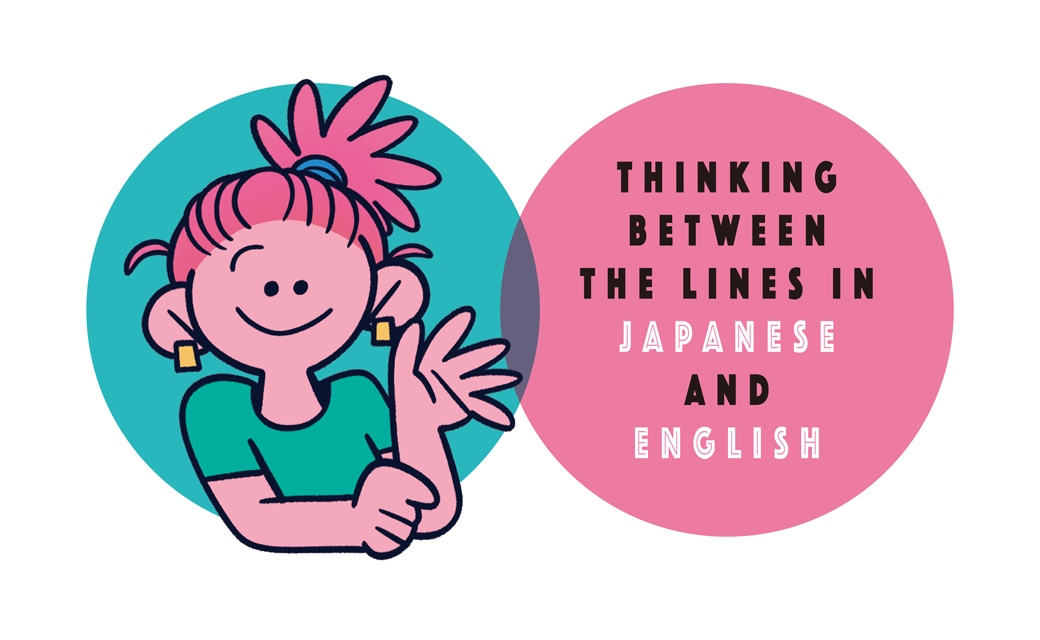パネルサインについて
2015年1月1日 更新
赤木かん子 児童文学評論家
学校図書館に必要なものは何か、どうやって作ればよいのか、壊れた本をどうやって修理すればよいのかなど、実際の写真を示しながらご紹介します。
かっこいいサインの作り方のひとつ、文字の切り抜きのやり方です。
「パネルサインの作り方」のときに紹介した、埼玉福祉会で売っている“パネルサイン”の中に、文字の表があります。その文字の書体を使うと、統一感のある部屋つくりができます。
1

これは“パネルサイン”(埼玉福祉会)の中に入っている文字表です。
必要な文字を拡大あるいはスキャンして使ってください。ほかのサインと同じ字体なのでしっくりきます。
2

拡大コピーしたところ。
3

ひと文字ずつにします。
「そ、つ、ぎ、ょ、う、お、め、で、と、う」です。
4

色画用紙をのせてみて配色を考えます。ここではわかりやすいようにこの色にしました。これがベストというわけではありません。
5

デザインカッターで切り抜きます。カッターのほうを動かすのではなく、文字のほうを動かすのが丸い線をうまく切るコツです。
6

切り抜いた黄色い文字を茶色の土台にのせたところ。
7

下の台紙の方にも“そ”がカットされました。
8

カットされた茶色の“そ”を黄色にのせてみたところ。
9

黄色の台に今度は切り抜かれたほうの“そ”をのせてみたところ。ただのっけただけだけど、手が込んでいるようにみえるでしょ。
10

台紙の色によって印象がかなり変わります。この色合わせはホント、センスが必要です。
困ったら、こういうことに才能のある子どもをスカウトしてやってもらってください。
11

これは市販の“桜の花びらの形の紙”の上に、文字だけ切り取って貼りつけたもの。
注意:のりは使わない。水分で紙がゆがんでしまうので。
ボンドをつまようじの先でちょっと取って、紙の上にぽっとのせるくらいでいいです。
それもべたっと全部貼りつけるよりは、端はとめないで浮かせておいたほうが臨場感がでます。
あとはどこに飾るかにもよりますが、似合うリボン、もしくはひもで飾ります。
赤木かん子
児童文学評論家。長野県松本市生まれ。1984年に、子どものころに読んでタイトルや作者名を忘れてしまった本を探し出す「本の探偵」として本の世界にデビュー。以来、子どもの本や文化の紹介、ミステリーの紹介、書評などで活躍している。主な著書に『読書力アップ!学校図書館のつくり方』(光村図書)などがある。
- このシリーズの目次へ
- 前の記事
-
次の記事