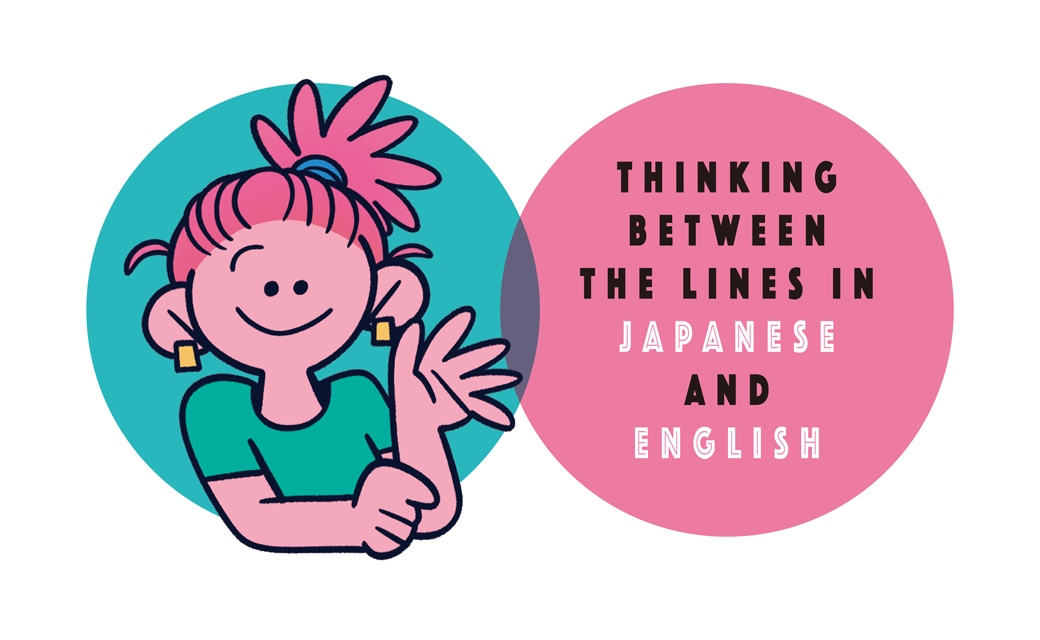読書Q&A 学校図書館(理論編)
2015年1月1日 更新
赤木かん子 児童文学評論家
どうすれば子どもたちが集まる図書館になるのでしょう。本のそろえ方や整理のしかたなど、学校図書館の作り方や運営方法に関する悩みにお答えします。
A(回答)
さて、Q9では自然科学の41から45までを紹介しました。今月は46(よんろく)からですが、
46は生物学一般
47は植物
48は動物
49は医学
が入っています。このとき、45までと46からとでは、とても大きな違いがあるんです。おわかりですか? そうです。41から45までは命のないもの…… 無機ですが、46からは命があるもの……有機です。そう考えるとすぐ覚えられます。
46の生物学一般には遺伝子や微生物が入ります。つまり無機から有機になっていくあいだがここで、次は、“生き物っていったら植物と動物よね”になり、動物の最後は人類ヒト科で、“ヒトに関する学問は医学よね”、になるんだなぁと覚えてください。でも、この最後の49は自然科学の中には入れないのが普通です。自然科学は人間の手が入っていないものをいいますが、医学は人間の手が入っているからです。だから記号として48と49を並べなくてもいいのです。今の日本では医療も発達しているので、むしろ医学には10個の分類のうち、一分類をあげてほしかったな、と思うくらいです。でも、そう決めちゃったものは仕方ない……ですから、自然科学と考えるときは41から48までだと思ってください。
この2桁目を第二次区分といいますが、まずは2桁目まででいいです。そうして分類は必要になったらやり始め、必要でなくなったらやめます。48の動物は、ただ“動物”だけでは、猫も鳥も昆虫もミミズも一緒のままで、わかりづらいし使いづらい、そもそも魅力的な棚には見えません。つまり人を魅きつける、 “あら素敵!”という陳列棚にならないのです。ですから、さらにもう一回10個に分けます。第三次区分です。
赤木かん子
児童文学評論家。長野県松本市生まれ。1984年に、子どものころに読んでタイトルや作者名を忘れてしまった本を探し出す「本の探偵」として本の世界にデビュー。以来、子どもの本や文化の紹介、ミステリーの紹介、書評などで活躍している。主な著書に『読書力アップ!学校図書館のつくり方』(光村図書)などがある。