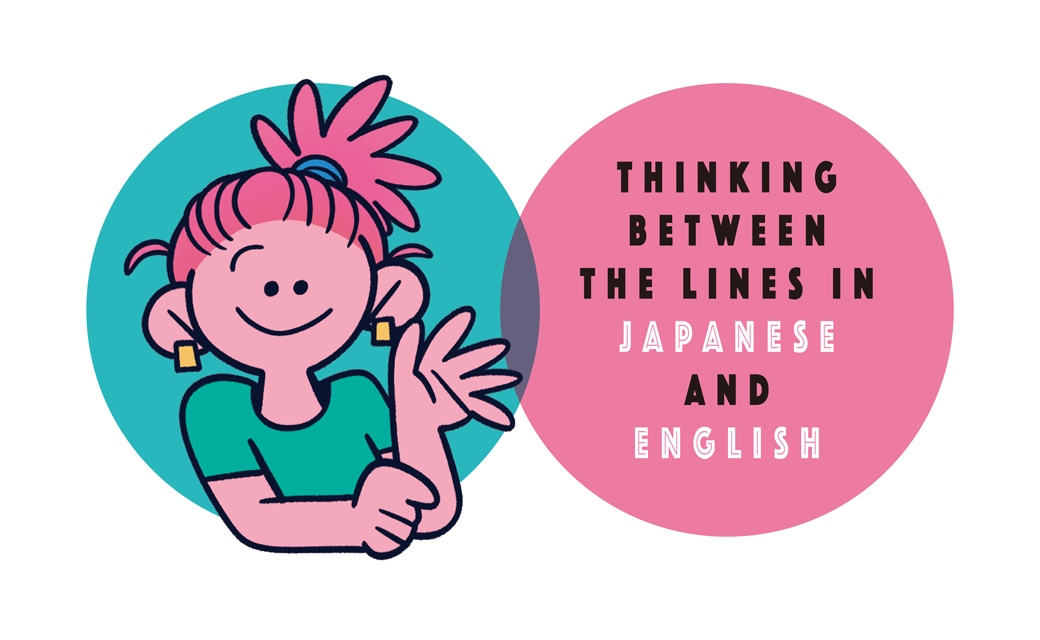英語をめぐる冒険
2016年1月29日 更新
金原 瑞人 翻訳家・法政大学教授
翻訳家として、大学教授として、日々英語との関わりの中で感じるおもしろさ、難しさを綴ります。
金原瑞人(かねはら・みずひと)
1954年岡山県生まれ。翻訳家、法政大学社会学部教授。法政大学文学部英文学科卒業後、同大学院修了。訳書は児童書、一般書、ノンフィクションなど400点以上。日本にヤングアダルト(Y.A.)というジャンルを紹介。訳書に、ペック著『豚の死なない日』(白水社)、ヴォネガット著『国のない男』(NHK出版)など多数。エッセイに、『サリンジャーに、マティーニを教わった』(潮出版社)など。光村図書中学校英語教科書「COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE」の編集委員を務める。
第11回 “教育費をめぐる冒険”
今回は、ちょっとタイトルを変えて、「教育費をめぐる冒険」にしてみたい。
昨年12月の「天声人語」にこんな指摘があった。
いかにも愚問であった。北欧フィンランドで大企業を辞めて会社を起こした人への取材中。子どもが10人いるというので、「事業に失敗したら教育費はどうしよう、と心配になりませんか」とたずねた。向こうはきょとんとしている。かの国では教育は大学まですべて無料、大学生の生活費まで出るのだ。出産の時には「育児小包」なる箱が届いて、肌着から防寒着までそろう。子どもは社会で面倒を見るとの考え方が確立している。

ほう、フィンランドはそんなに豊かな国なのかと不思議に思った人も多いと思う。たしかに、学費も教材費も給食費も無料で、福祉、医療制度も日本などとは段違いに整っている。
しかし消費税は23%、個人の所得税率は50%前後。それで国民の理解が得られているところが素晴らしいのだ! 文化、福祉、教育をないがしろにする日本とはここが大きく違う。天声人語も、ここを書かないでどうするといいたい。
男女の社会的格差もほとんどなく、「育児小包」の例をみてもわかるように、女性にとってはとても働きやすい環境が整備されている。
しかし、それは女性も社会的に男性と同じ責任を持つということであり、たとえば、専業主婦という概念はない。仕事のできる環境にあって働かなければ、たんなる失業者である。日本から、夫の北欧長期出張についていった妻が当惑する例も多いという。
それはともかく、今回、なんでこんな話題を出したかというと、「Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled--and More Miserable Than Ever Before」(今日のアメリカの若者はかつてなかったほど自信にあふれ、積極的で、恵まれている──にもかかわらず、なぜ、かつてないほどみじめなのか)というタイトルのアメリカの若者論を読んでいて、やはり教育費の問題が出ているからだ。
作者はJean M. Twenge。2006年の出版だからもう10年も前になるが、現代アメリカの若者の実態を適確にとらえた若者論としてベストセラーになり、いまでもよく読まれている。ここで取り上げられている若者というのは主に1970年代から90年代に生まれたアメリカ人だから、当時、35歳から15歳までの人々と考えていい。
この本には、アメリカの若者が「かつてないほどみじめな」理由が、数十年にわたる心理的、経済的、社会的な細かいデータや、若者の生の声をもとに列挙されている。興味のある方はぜひ読んでみてほしい。
そのなかで教育費について書かれている箇所を引用してみよう。
And don't forget to save for college for those kiddos! In Oregon, colleges and universities cost 34% of the average family's income, up from 25% in 1994. Four years at an Ivy League school now tops $160,000; the average private college, $110,000. Even four years at most public universities will run you at least $40,000 (for example, it's over $60,000 for four years at san Diego State, including room and board).
この費用は学費だけでなく、寮費なども含んでいる。しかしこれは10年前の相場で、もちろん現在ではかなり上がっている。10人の子どもを全員、アイヴィーリーグを卒業させるには2億円以上必要になる。フィンランドではともかく、アメリカでは、その付けは子どもに回り、卒業してから奨学金(というより学資ローン)の返済に追われることになる。
1996年に出版エイジェンシーに入って、サリンジャーの担当もすることになった女性のエッセイ集『サリンジャーと過ごした日々』(柏書房)には、こんな箇所がある。
学生ローンの請求書のほうは、それよりはるかに恐ろしかった。借金の総計については──不吉なことに──記載がなく、五月分の返済金を十日以内に送金するようにとだけ指示があった。四百七十三ドルだ。ほぼ二週間分の給料だった。家賃を払ってしまうと給料はきれいさっぱりなくなる。
フィンランドの数字もアメリカの数字もすごい。
さて、今の日本の教育環境をどう考えればいいのだろう。
Illustration: Sander Studio