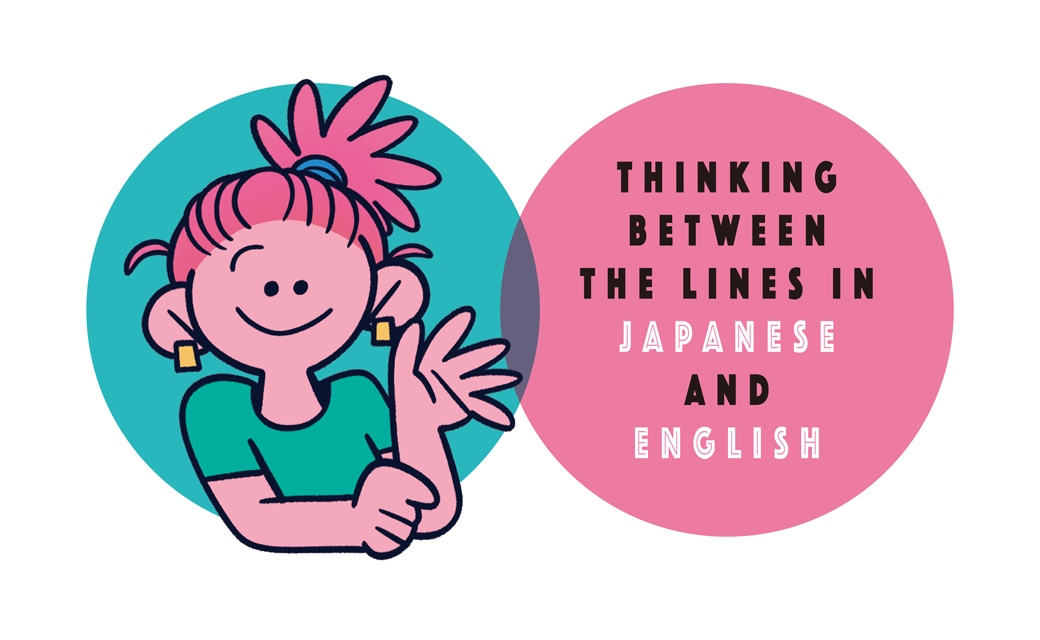英語をめぐる冒険
2015年3月31日 更新
金原 瑞人 翻訳家・法政大学教授
翻訳家として、大学教授として、日々英語との関わりの中で感じるおもしろさ、難しさを綴ります。
金原瑞人(かねはら・みずひと)
1954年岡山県生まれ。翻訳家、法政大学社会学部教授。法政大学文学部英文学科卒業後、同大学院修了。訳書は児童書、一般書、ノンフィクションなど400点以上。日本にヤングアダルト(Y.A.)というジャンルを紹介。訳書に、ペック著『豚の死なない日』(白水社)、ヴォネガット著『国のない男』(NHK出版)など多数。エッセイに、『サリンジャーに、マティーニを教わった』(潮出版社)など。光村図書中学校英語教科書「COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE」の編集委員を務める。
第1回 裏切り者のぼやき
“Translator, traitor.” 訳せば、「翻訳家、裏切り者」。イタリアの古いことわざだが、英語でもよく使われる。翻訳はいい加減なものであって、あてにはならないという意味だ。もう少していねいに説明すると、ある言語で書かれたものを別の言語に訳すときには、必ず何かが抜け落ちたり、余分なものが付け加わったりする、端的にいえば、完璧な翻訳などありえないということだ。
長年、翻訳をしていると、この言葉のいいたいことは痛いほどよくわかる。
たとえば、「吾輩は猫である」を英語に訳すと、“I am a cat.”になる。日本人としては悲しい。おいおい、そりゃあないだろうといいたくなる。英語の一人称は“I”しかない。「吾輩、拙者、それがし、私、あたし、俺、おいら」などなど、訳せばすべて“I”だ。そして“I”が主語の場合、be動詞は“am”だ。乱暴にいってしまえば、「である」が“am”になってしまう。

「猫」を“cat”と訳すのはいいんじゃないかという指摘が出てきそうだが、猫は「にゃあ」と鳴くが、“cat”は“mew”と鳴くし、欧米の猫はでかい。猫は2音節だが、“cat”は1音節だ。まったく、英語にしてしまうと、原文のリズムもニュアンスもすっかり変わってしまう。
この例だけでも翻訳家がいかに裏切り者かはよくわかる。
アメリカのバーやパブの壁に、女の子が両手にこんな文句の書かれた紙を持って叫んでいる絵がかかっていることがある。
“Don't shoot the piano player. He is doing the best he can. ”「ピアニストを撃たないで。いっしょうけんめい弾いてるんだから」というジョークだ。われわれは、“Don't shoot the translator. He is doing the best he can. ”と叫びたい。
たとえば、「吾輩は猫である」にしても、とりあえず、いろんな訳を考える。“Call me your highness cat. ”と訳したらどうか? しかし、これだと「吾輩を猫陛下と呼べ」だから、原文とはちょっとちがう。戦後の有名な英文学者が、せめて“Here I am ? a Cat. ”くらいに訳したらどうかと書いているが、これも、「オレ様登場──猫だ」といった感じで、ちがう。となると、結局、“I am a cat. ”が無難かなあと、ここに落ち着いてしまう。しかし、そこにいたるまでに大きな葛藤があるのだ。
だけど、やっぱり翻訳家って、裏切り者じゃん、といわれそうだが、それでも頑張っているのだという話を次にしようと思う。
Illustration: Sander Studio
- このシリーズの目次へ
-
前の記事
- 次の記事