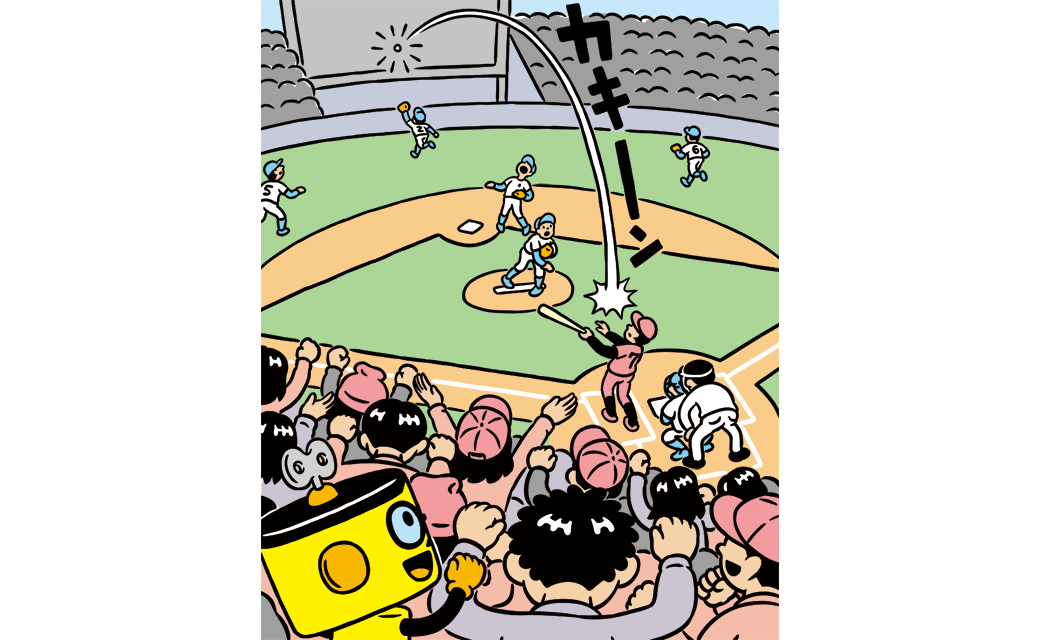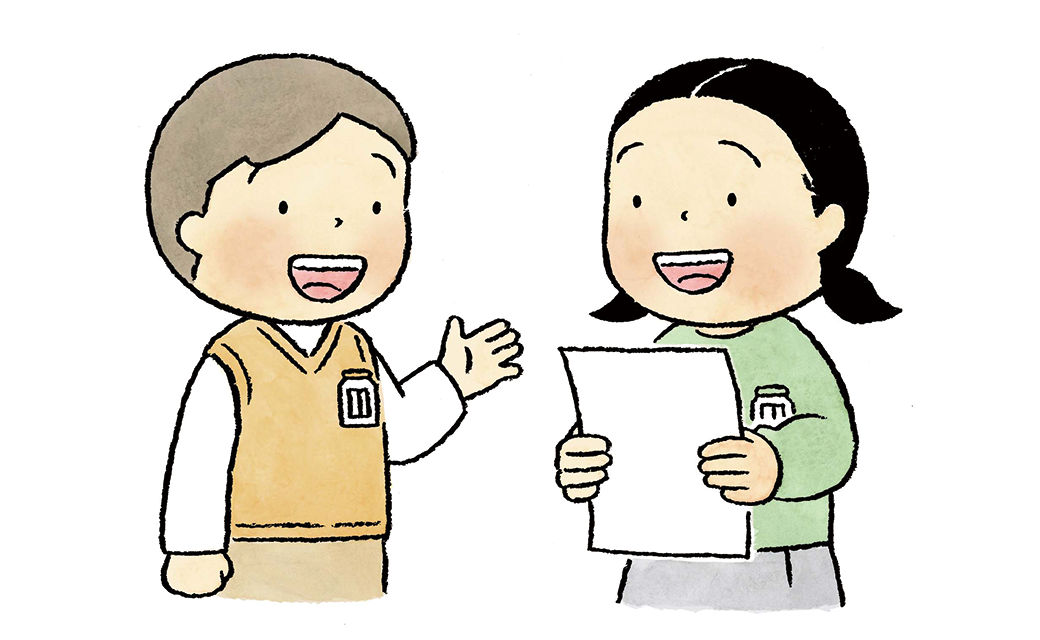「こんな授業ができます!」 令和6年度版小学校国語
2024年4月26日 更新
櫛谷孝徳 相模原市立清新小学校教諭
3年上巻「文様/こまを楽しむ」の授業づくりのアイデアを紹介します。
筆者の書き方の工夫を読み取ろう
単元観
本単元で、子どもたちは段落の役割や文章構成などを学ぶ。「文様/こまを楽しむ」は、事例のまとまりで段落が構成されており、「はじめ」「中」「おわり」を捉えるのに適した教材である。「文様」での学習を「こまを楽しむ」に生かすように単元計画を立てることが大切である。
「文様」を読むと、「はじめ」には「どんなことを願う文様があるのでしょうか。」と「問い」があり、その「答え」を探りながら読むことで中心となる語や文を捉えることができる。「おわり」は、「このように」というまとめとなる接続詞に着目することが重要である。
教材の特徴として、事例の順序を考えてみたい。どちらの教材も、子どもたちにとって身近なもの、分かりやすいものから順番に説明されている。各段落で同じような書かれ方をしているのだが、最後の事例のみ、文末が過去形で終わっている。そのような表現にも立ち止まりながら、筆者の書き方の工夫を捉えていくとよいだろう。
単元の指導目標
◎文章構成を捉えながら、全体と中心など情報と情報の関係について理解することができる。[知(2)ア]
◎段落相互の関係に着目しながら「はじめ-中-おわり」の構成を捉えることができる。[思C(1)ア]
○段落の役割について理解することができる。[知(1)カ]
○中心となる語や文を見つけることができる。[思C(1)ウ]
○粘り強く、段落相互の関係に着目しながら文章構成を捉え、いちばん遊んでみたいこまについてまとめ、グループで話し合う。[学びに向かう力、人間性等]
単元の授業過程(全8時間)
| 次 | 時 | 学習活動 | 評価規準と評価方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1・2 | ①「文様」の題名や絵から気づいたことを話し合う。 ②筆者の書き方の工夫を考える。 ③「問い」に対する「答え」や「はじめ」「中」「おわり」の構成を捉える。 |
○段落の役割や文章構成を理解し、学習に見通しをもっている。[発言] |
| 2 | 3〜7 | ①「こまを楽しむ」を読み、「問いをもとう」や「もくひょう」をもとに学習計画を立てる。 ②文章の二つの「問い」を確認する。 ③段落に番号をつけ、文章全体を「はじめ」「中」「おわり」に分けて、構成を捉える。 ④「問い」に対する「答え」を探し、「中」の書かれ方を読み取る。 ⑤「文様」と「こまを楽しむ」の「答え」の書かれ方の違いを読み取る。 ⑥筆者が、6種類のこまをどのような順序で説明しているかを考える。 ⑦文章全体の「おわり」の役割を捉える。 ⑧6種類のこまが、「回る様子」と「回し方」を楽しむこまで分けて書かれていることを捉える。 |
【知】段落の役割について理解している。[段落番号] 【知】こまの種類と楽しみ方などを捉え、全体と中心を理解している。[記述・発言] 【思C】文章全体を「はじめ」「中」「おわり」で捉えている。[記述] 【思C】「問い」に対する「答え」を捉えるなど、中心となる語や文を見つけている。[サイドライン] |
| 3 | 8 | ①いちばん遊んでみたいこまとその理由をノートにまとめる。 ②いちばん遊んでみたいこまについて、グループで話し合う。 ③学習全体を振り返る。 |
【態】いちばん遊んでみたいこまについてノートにまとめ、グループで話し合おうとしている。[記述・話し合い] |